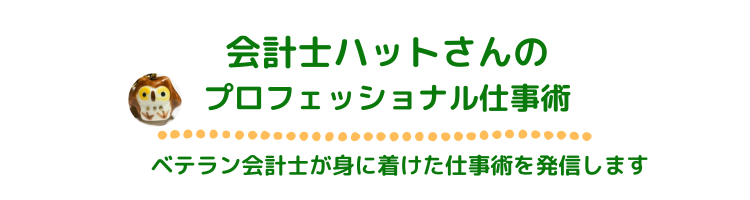今回は「問題解決に向けた議論の前にしておくべき2つのこと」という話しをします
どんな職場でも改善しなければならない問題というのは多かれ少なかれ存在します。そのため、改善に向けて上司・部下・同僚などで議論する風景は珍しくもありません。今回はそんな問題解決に向けた議論をする前段階として、次の2つのことを明確にしておいた方がいいですよ、という話しをします。

定義と尺度・基準を明確にすること
まずは第27回目の記事(問題解決に向けた議論の前にまず行うべきこと(関係者の目線(認識)合わせ))の振り返りから
今回の説明に入る前に確認しておきたいことがあります。第27回目記事で、問題解決に向けた議論の大前提として、関係者間で目線が合っていない状態でいくら議論をしたところで意味がないですよ、だから目線を合わせるところから始めましょう、という提案をしました。その時に説明したのが下記図です。

問題解決のテーマが単純なもの、例えば「在庫受払ミスの撲滅」のような紛れがないテーマだったら、上記のように「現状・実態(AS IS)」と「あるべき姿(TO BE)」の目線合わせから始めて問題ありません。
今回の記事で言いたいのは、上記よりもさらに前の段階の話しです。問題解決のテーマが少しでも複雑さを増したら上記目線合わせの前にもう一工夫したほうがいいですよ、と言いたいのです。
定義と尺度・基準を明確にすること
問題解決のテーマが先ほど挙げた「在庫受払ミスの撲滅」のような単純なものであれば神経質になることもないのですが、改善すべきテーマが「品質」とか「創造性」とか「効率性」などの場合、関係者それぞれの認識が異なるために議論がかみ合わないといったことはよくあります。テーマに関するそもそもの認識が関係者間でズレているのです。そうなると、議論の前に、①定義と、②評価の尺度・基準、について目線合わせ(認識合わせ)をしておくが重要になります。

この点について、松下通信工業の常務だった唐津一氏が自著の中でとても分かりやすい説明をしています。少し長い引用になりますが、参考になるので紹介させてください。
警察庁を困らせた質問
もうひと昔前になるが、日本の都市部で道路事情が急速に悪化しはじめたころ、警察庁の中に道路混雑を扱うための委員会ができ、その第一回会合に出席したことがある。事務局から 「なぜこういう委員会をつくったか」という趣旨説明が長々とあったが、要はこういうことだった。近年、東京その他の大都市道路が非常に混むようになった。そこでこの混雑を解消するために、この委員会を設置したのだ、と。そこで私は質問してみた。
「いま、混雑という言葉をさかんにお使いになりました。道路が混雑するということは、いったいどういうことですか?」
ほかの委員たちは皆、あきれたような表情を浮かべ、「そんなこと、わかりきっているじゃないか」といわんばかりであった。だが、じつは誰もわかっていないのである。
問題の中身を知らずして、何をどう解決しようというのか。「混雑とは何か」が具体的に定義されなければ、どうなれば混雑が解消したことになるのかわからない。プロジェクトの目的と評価システムを具体的に設定してもらいたくて、私は質問したのである。(中略)
「ひとくちに混雑の緩和といってもいろいろあるでしょう。たとえばある地点からある地点へ行くのに従来は30分かかったところが、新しいやり方にしたら15分で行けるなった。これを混雑が緩和したと考えるなら、そのようなクルマの流れに規制する方法があります。また、ある道路があって、これまで一時間に1000台しか走れなかった。それが新しいやり方にしたら1200台走れるようになった。これも混雑の緩和と見ることができる。しかし、いま申し上げた二つのケースでは、やり方を変えなくてはいけません。だから、混雑をなくすといっても、混雑とは何かという共通理解をもつところからはじめないと、うまくいかないのです」目的によってまったく異なる解決策
(出典)「ビジネス難問の解き方」唐津一(注)ハットさんが一部太字にした。
ちなみに前者は、移動時間を短縮することを目指すケース、後者は、道路の容量を増やすことを目的とするケース。どちらの目的を設定するかで、当然のこと、有効な交通規制の方法論は変わってくる。だから、原点にかえって、目的を明確にすることが先決なのである。(中略)
混雑とは何かという原点から議論せず、ただなんとなく解決を話しあっているだけでは、こうした結論にたどりつけなかったかもしれない。目的を具体化し、評価の尺度を明らかにすることで、さまざまな実験が有効に機能する。実験結果をその評価の尺度にしたがって分析し、より目的に近づけるにはどうすればいいかを考えてまた実験する、といったひとつの思考サイクルが確立されるからである。
上記で唐津氏が指摘するように、よくありがちな議論は「ただなんとなく解決を話しあっている」という進め方です。「●とは何かという原点」から議論することはよほど意識しない限りありません。この場合、どういう状態になったら●が改善したと言えるのかということもぼんやり認識しているだけです。
例えば、「品質改善」に向けて議論しているときに、そもそも「品質」の定義が漠然としている(または定義がない)ので、「品質改善の程度」についてもどんな尺度で測定すべきかが明確になっていないなんてことは実務ではザラです。苦し紛れに「品質改善の程度」の尺度・基準を「内部監査室の監査による指摘の数」としていた実例を見たことがあります。
そんなことにならないようにどんなテーマであっても改善に向けた議論をする前段階で、次の2点を明確にしておくことをお勧めします。
①定義
②評価の尺度・基準
KPIの議論も同じこと
ところで、最近ビジネスの色々な現場では、業績管理評価のための重要指標である KPI(Key Performance Indicator)という概念を導入しています。この KPI として何が適切なのかという議論も今回の議論とまったく同じと考えています。英語で KPI(Key Performance Indicator)とか言われると何となく米国の知らないマネジメント手法のような印象を受けますし、いまひとつよく分からないけど当社も業績管理数値として KPI を決めなければいけないね、というような安直な考えを持つことは珍しくもありません。しかしながら、大事なことは、KPI という言い方をするかどうかはともかくとして、今回の記事で説明したように、本来的には①定義と②評価の尺度・基準について、関係者で入念に議論して共通認識を持っておくこと(目線を合わせをしておくこと)です。KPI を設定する際にはこの考え方を忘れないようにしなければなりません。
【今回の記事に関して読んで欲しい哲学の文献】
今回の記事は、改善に向けた議論をする前段階で、①定義と、②評価の尺度・基準、の2点を明確にしておくべきだというものでした。この点に関していつも思い起こす考え方があります。土屋賢二氏の「ツチヤ教授の哲学講義」という本の中で紹介されている考え方です。実に示唆に富む内容なので、とても長い引用になって恐縮ですが、ぜひともお読みいただきたくここで紹介させてください。
測定法と本質
(出典)「ツチヤ教授の哲学講義 哲学で何がわかるか?」土屋賢二(注)ハットさんが一部太字にした。
今日言ったことに補足しておきたいんですけど、さっき、「五分間」という時間の測り方を問題にしましたよね。でも、これに対して、時間をどうやって測定するかということは、時間そのものが何であるかということとは問題が違うんじゃないかと思われるかもしれません。まず時間が何かの形で存在していて、それを後から測るのが測定だと思えますよね。だから、測定をいくら明らかにしても、時間そのものがどんなものかは関係がないと思う人がいるかもしれません。でも実際には、どうやって測るかは非常に重要なんです。測定の仕方は本質に直結しているんです。
たとえば、「一メートルとは何か」ということが問題になったとします。一メートルをどうやって測るかというと、定規で測りますね。その定規は、パリのメートル原器か何か、そういうものを基にして作られています。でも、これはウィトゲンシュタインという哲学者が言っていることなんですけど、かりに定規がゴムでできていたとしますね。
大きく伸び縮みするゴムで測ることになっていたとするんです。「一メートル」の測り方をそう決めたとします。つまり、「一メートルを測る」というのはどういうことかというと、ものさしをあてがって、ものさしと同じ長さかどうかを調べるんだけど、そのものさしはゴムでできていて、いくら伸びても縮んでも同じ長さだと決めたとします。もしそういう規則を採用する社会があったら、その社会で「一メートル」と呼んでいるものと、われわれの社会で「一メートル」と呼んでいるものは、まったく違ったものになると思うんですね。そういう社会では、畳の縦と横が同じ長さということになったり、この大学の大教室と東京ドームが同じ広さということになったりしますからね。だから、測定の仕方が違えば、長さがどんなものかということについても、まったく違った理解が成り立つことになると思うんですよね。つまり、長さをどうやって測るかということは、長さが何であるかということに非常に密接な関係があるんですね。
時間についても同じです。測定の仕方によって、時間がどんなものかが違ってきます。たとえば、それぞれの人が五分たったと思えば五分たったことになる、という仕方で五分間という時間を測ることにしたり、腹の空き具合で正午かどうかを決めたりすることになれば、時間とは何かということが、今とはまったく違ったものになります。そうなれば、自分が二〇歳だと思えば二〇歳になりますから、年齢制限とか、先輩後輩の区別もなくなるし、待ち合わせも成り立たなくなりますし、電車の時刻表やテレビの番組表も意味がなくなってしまいます。
痛みの本質と測定法
(出典)「ツチヤ教授の哲学講義 哲学で何がわかるか?」土屋賢二
測定とは違うかもしれないんですけど、ぼくらは「痛い」ということばを使っています。痛いかどうかはどうやって判定しますか? 簡単です。本人が痛いと思えば痛いことになりますね。痛いかどうかということは本人が決めることです。本人が痛いと思いさえすれば、痛いことになる。だから、本人が絶対的な権威です。かりに「歯が痛い」 と言う人がいて、歯医者がその人をどんなに調べてもレントゲンをとっても何をしても 異常がないとします。それどころかその人には神経もないことが判明したとします。そ れでも、歯医者が「お前が〈痛い〉って言うのは間違っている。痛いはずがない」とは言えないと思うんです。患者が痛みを感じているかどうかは、本人が決めることです。 だから医者としては、「非常に考えにくいことなんだけども、この患者は神経がないのに痛みを感じている」と言うしかないと思うんですよね。「お前は本当は痛くないんだ」っていう言い方をすることはできません。
われわれはそういう仕方で「痛い」ということばを使っていますけど、でもかりに、これからは「痛い」ということばをそういうふうに使うのをやめようということになったとします。痛いかどうかを決めるのは、本人が決めるんじゃなくて、客観的に決めることにしようということになって、たとえば、歯については、虫歯がC2以上になったら「この歯が痛い」ということに決めたとします。その場合、患者が「痛いんです」と訴えても、医者が「いや、まったく痛くない」と否定することがありえます。「C2以上じゃないから、お前は痛くない。お前が〈痛い〉と言うのは間違ってる」という言い方ができます。つまり、この場合は、痛いかどうかは虫歯の物理的状態がどうなっているかによって決まります。本人の気持ちに関係なく、客観的な手続きによって痛いかどうかが決まるんですね。本人が何も感じないのに「お前は痛いんだ」と言われることも あるし、本人が「痛い」と言っても「本当は痛くない」という事態がありうることになります。
それに対してわれわれの社会で使っている「痛い」ということばなら、本人が痛いと思っているかどうかが痛いかどうかを決める最終的な決め手になっています。この場合と、痛いかどうかを客観的な手続きで決まるように変えた場合を比べてみると、痛いかどうかをどうやって決めるのかということが違っているだけなんですけども、でも、「痛みとは何か」ということがまったく違うものになってしまうと思いませんか? 時間の場合もそうなんですけども、時間の測り方というのは、時間本体が何であるかということとは間接的なつながりしかないみたいに思えますけども、実は本質的なつながりがあるとぼくは思うんです。われわれは五分たったかどうかを、時計を使って決めているわけですけども、そのことは、「時間とは何か」という問題にとって、本質的だと思うんですよね。
つまり、抽象的な概念になればなるほど定義(本質)を明確にしないまま議論することは意味がないし、また、定義(本質)を考えるということは、すなわち測定法もセットで考えることなのだと教えてくれます。
この考え方は、私が会計士としてクライアントの業務改善の助言をする際にも大いに役に立ちました。皆様にも参考になれば幸いです。
今回のまとめ
問題解決に向けた議論をする前にして、次の2つのことを明確にしておくこと
①定義
②評価の尺度・基準

おすすめ図書
記事本文でも本書からの一説を紹介しましたが、それ以外にも問題解決に向けて参考になることがたくさん書いてあります。書名タイトルの「ビジネス難問の解き方」からも想像がつくと思いますが、本書がテーマとしているのは問題を発見し、それを解決する思考法です。2016年出版なので若干古い本ではありますが、著者が提唱する考え方そのものは今でも大いに参考になります。とはいえ、ものすごく斬新な内容のことが書いてあるわけでもないので、すでにたくさんのビジネス書を読んでいる人や実務で多くの困難を乗り越えてきた人にとっては目新しい内容は少ないかもしれません。いずれにしても、本書は堅苦しくなく簡単に読めますので、本屋で見つけたら手に取って中身を見て欲しい本です。

「本質(定義)と測定法は直結する」という考え方は大事ですね。