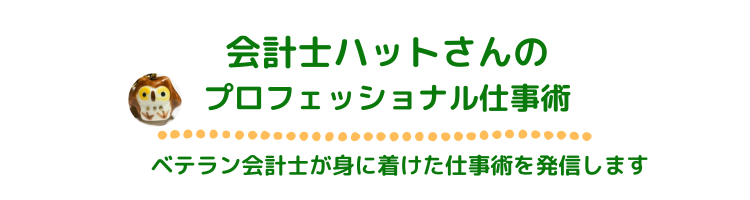今回は「プロなら口先だけのきれいごとを主張するだけで終わりにしてはいけない」という話しをします。
第100回目の記事(「2階級上の立場で考えろ」と言われて私が心がけていたこと)では「意見だけ言っても自分でやらないなら意味がない」というようなことを書き、併せて大前研一氏の「有言不実行の“社内評論家”も役には立たない。“有言実行”が大切」という言葉も紹介しました。
今回の記事も同じような内容なのですが、第100回目の記事と異なるのは、「そもそも誰もが反対しないような一般論を主張するだけで終わらせるな」ということです。もっと踏み込んで言うならば「誰も反対しないような一般論を言ったところで何も言っていないのと同じだ」と言いたいのです。今回はそんなお話しをします。
今回の記事で伝えたいことを先に要約すると…
今回の記事でお伝えたいことはシンプルで要約すると次のようになります。
◆プロなら口先だけのきれいごとを主張するだけで終わりにしてはいけないと肝に銘じること
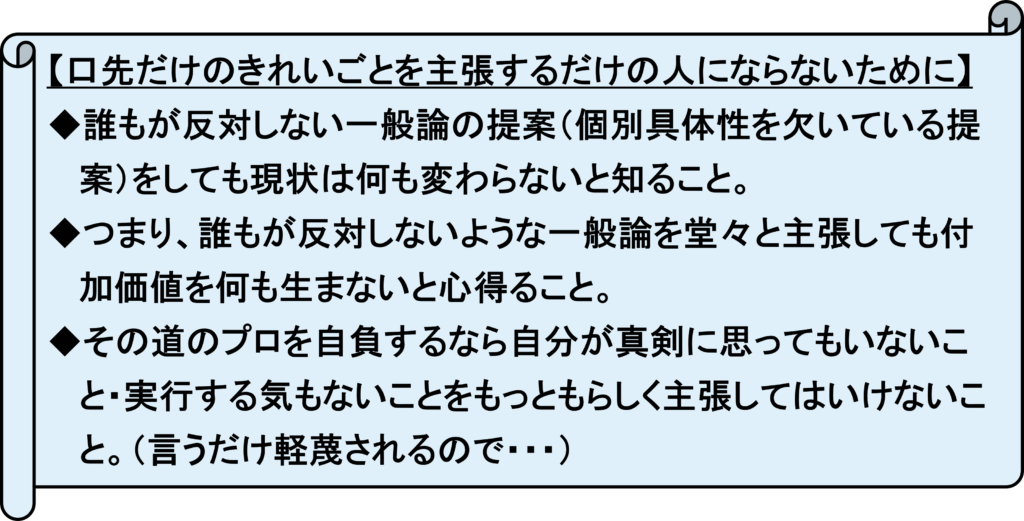
このブログは仕事経験が比較的浅い方を読者として想定していますが、もし読者の中に何かの専門家・プロと言われる立場の方がいればアドバイスです。誰もが反対しないような正論だけを主張しても基本的に何かの付加価値を生み出さないし、また、そのような主張をしたところでリスペクトもされないということです。さらに言えば、リスペクトをされないどころか「あの人はただの評論家だよね」と陰口をたたかれ、軽んじられることすらあります。
したがって、特にプロならば「口先だけのきれいごとを主張するだけで終わりにするのはやめましょうね」と申し上げたいのです。
今回の記事の内容はこれだけなので忙しい方はここで読むのを止めても問題ありません。
以下では、誰もが反対しない一般論を主張してもあまり意味がないことを痛感させられる文章として、香西秀信氏「反論の技術」という本の一節をご紹介させてください。
誰もが反対しない一般論を主張することが意味ないと痛感させられる文章の紹介
「誰もが反対しないような一般論を主張しても意味がないこと」を考えるうえでどうしても紹介したい本の文章があります。香西秀信氏「反論の技術」という本の以下の文章です。
すごく長い引用になるので大変恐縮なのですが、非常に皮肉たっぷりの辛辣な内容であり、自分の意見を振り返るのにはとても良い教材と言えます。ぜひここで紹介させてください。
<ハットさん注:香西秀信氏はまず教科書に載っている意見文を紹介する>
(中略)このごろは、「命がどんなに大切か。」ということについて書いた本が、たくさん出ています。わたしも、本当に命は大切だと思います。たとえ、あり一ぴき、花一輪であろうとも、 命は大切ではないでしょうか。(中略)
わたしは、たとえどんなことがあっても、命をそまつにするような人間には、なりたくありません。この学校を卒業するまで、しいく委員として、動物の命を預かり、大切に育てていきたいと思います。この文章を読んで感じる最大の疑問は、この生徒は読者に何を伝えようと思ってこれを書いたのかということである。「本当に命は大切だと思います」と訴えかけているが、読者は「命は大切だ」ということを知らないと思っているのだろうか。もし知っていると思っているのなら、 なぜ殊更それを主張する必要があるのだろうか。知ってはいるがその知り方が足りないので、 自分が一肌脱いで蒙を啓いてやろうと思っているのだろうか。あるいは、生徒の中には「命は大切ではない」と信じる「不逞の輩」がいるので、こういう意見文を書くことによってそのねじくれた精神に鉄槌を下して矯正してやろうと思っているのだろうか。また、これを読んで、 読者に何か変化が起こるか。今までは命が大切だとは思わなかったが、これを読んで本当に命は大切だということが分かったと前非を悔いる読者がいるのだろうか。(中略)
(出典)「反論の技術 その意義と訓練方法」香西秀信(注)ハットさんが一部太字にした。
このような、誰も反対しないことを意見として主張する癖をつけてはいけない。こんなものを意見文として書かせている間は、議論・討論の能力は育たない。「意見を言う」ということの意味が分かっていないからである。
(中略)
「たとえ、ありいっぴき、花一輪であろうとも、 命は大切ではないでしょうか」などと、思ってもいないことを書くべきではない。もし本当にそう思っているなら、自分の命を維持することさえ難しくなる。ジャイナ教の信者のように、 人間が生きていくこと自体が動物・植物の殺生の上に成り立っているとして、何も食べずに餓死することを選ぶしかなくなる。そこまで極端でなくとも、「ありいっぴき、花一輪であろうとも、命は大切」だと書きながら、蚊は線香で麻痺させる、蠅は殺虫剤で撃墜する、油虫はスリッパで叩き潰すというのであれば、一体何のための意見なのか。
(中略)「命は大切だ」という意見文を書いてきた生徒には、新薬を一つ開発するのにどれ程多くの動物が残酷な実験で殺されているかという事実を教える。そして問いかけてみる。「君は動物の命を守るために、新薬の開発を止めるべきだと思う。 それとも、人間が生きるためには、他の動物を犠牲にしてもいいと考えるか。さあ、『あり一匹、花一輪であろうとも、命は大切』だと主張する君の考えを聞こう。」(以下略)
<ハットさん注:香西秀信氏はもうひとつ教科書にある意見文を紹介する>
「ごみのない住みよい町に」
(中略)
ごみのない住みよい水口町。いつか、祖母が言っていたような山によみがえり、また、一人一人の心の中にも、いま以上に温かい心が生まれてくることを願って、わたしは、一日一つのごみ拾いを提案します。(出典)「反論の技術 その意義と訓練方法」香西秀信(注)ハットさんが一部太字にした。
ここで問題にしたいのは、一番最後の「わたしは、一日一つのごみ拾いを提案します」という文章である。この生徒は、自分の文章の読者を一体どういう人達に想定しているのだろうか。 もし、担任の教師や同級生に読ませるつもりで書いたのなら、この提案はほとんど意味がない。 たかだか四十数名が、一日に一つごみを拾ったところで焼け石に水である。あるいはもし、水口町の全員に読ませるつもりで書いたのなら、そのためにどのような手立てを講じたのか。まさか何の努力もせずに、この提案が念力で水口町の人間に伝わると思っているわけでもあるまい。一体どういう手段で町の人間に読ませるのか。
しかし、たとえ水口町の全員が読んだとしても、この提案に何か実際的効果があるだろうか。 これを読んだ人が、本当にこの提案どおりの行動をすると思っているのだろうか。自分はどうか。今でも毎日一つずつごみを拾っているか。
このような問いかけを繰り返しても空しいだけなので、このくらいで止めにする。要するにこの生徒は、誰も正面切って反対しないような事柄を、口先だけで提案しているにすぎない。
しかも、その提案は、誰も従わないことが分かっており、自分でさえもおそらく長くは実行する気のないようなものなのだ。こんな提案など、おまじないのようなものである。町中で見かける、「世界人類が平和でありますように」という張り札と同じだ。福田恆存氏が次のように言っている。「ひとびとは『入り口ふさげば一人で満員』なる標語を掲げ、この標語の存在が何らかの実際的効果を発揮するかのやうな錯覚に陥つて、この安心のうちに行為への責任を免れてゐる。たしかに標語の氾濫してやまぬゆゑんである。」はっきり言って、この生徒は悪質だ。 自ら「意見を言う」という行為を軽く見て、それを馬鹿にしているからである。(以下略)
私が香西秀信氏の上記文章を読んだのは仕事を始めて7年目の時でした。今までの自分の意見がいかに弛んだものだったかを痛感させられました。それ以来、「誰もが反対しないような口先だけのきれいごとを主張するだけではゆめゆめ終わりにしない」ことを自分に課しています。ぜひ皆様も香西秀信氏の上記文章をもとに自分の意見を厳しく振り返って頂き、今後に生かしてもらえればうれしいです。
今回の記事本文は以上です。
【今回の記事を公認会計士として監査先に対して行う改善提案で考える】
今回の記事で言いたかったのは「誰もが反対しないような口先だけのきれいごとを主張するだけで終わりにするな」ということですが、これを私の仕事の分野で考えてみるとどうなるか。あくまでも一つの例として取り上げます。なお、会計領域などに関心のない人は、このコーナーは読み飛ばして構いません。
私は公認会計士として財務諸表監査を専門に仕事をしています。監査の過程では、気がついた改善事項を監査先の経営者に伝えます。この改善事項を経営者に伝える時、経験値の低い会計士にありがちなのは次のような短絡的な「正論」だけを主張することです。
◆人員が足りないから人員をもっと採用すべきだ。
◆システムが脆弱だからシステムを強化すべきだ。
◆収益力が低いからこのままいけば減損だ。
これらの主張そのものは正論ですから誰からも反論されることはありません。言ってみれば、会計士にとっては相手の弾丸が飛んでこないような場所から唱える安全な主張です。しかし、指摘を受ける経営者の方からすれば、「今更そんなことは会計士に言われなくても分かっている。問題はどうするかであって、それが簡単ではないから困っているんだよね」と感じています。だからこそ経営者は、心の中では「会計士のように正論だけ言っておけばいい人は気楽でいいよね」とか「会計士って経営のことは何にもわからず、ただの会計バカだよね」のように思っている可能性が高いと想像しています。
そうならないためには、個別事象ごとに具体的な解決策(選択肢)・実行可能性・解決策の効果・解決策実施にあたっての前提条件や時間軸などを経営者と丁寧に議論することが大事です(なおこの点に関しては第96回目の記事(何かを提案するときに意識すべき4つのポイント)もぜひご参照ください)。それらを無視して一方的に「正論」だけの改善提案を主張してもプラスの効果を何も生み出しません。だから、私が上司としての立場にあるときには、部下に対してそのことを何度も何度も繰り返し強調したし、部下が主張する「正論」に対してあえて煽るような、時には無茶苦茶な反論もぶつけて部下の思考を揺さぶるようにもしていました。これもそれもすべて「プロなら口先だけのきれいごとを主張するだけで終わりにしてはいけない」ことを徹底するためです。
いくら誰も反対しない「正論」だとしても自分が本気で思ってもいないことを口先だけで主張するのは控えなさい、ということは、言い換えれば、主張するときは心の底から本気で自分が考えている意見を言えということです。
これはプレゼンするときでも同じです。このことを第97回目の記事(プレゼンで最も大事なこと-心の底から伝えたい内容なのか)で書いています。ご関心があればどうぞ。
今回のまとめ
◆プロなら口先だけのきれいごとを主張するだけで終わりにしてはいけないと肝に銘じること
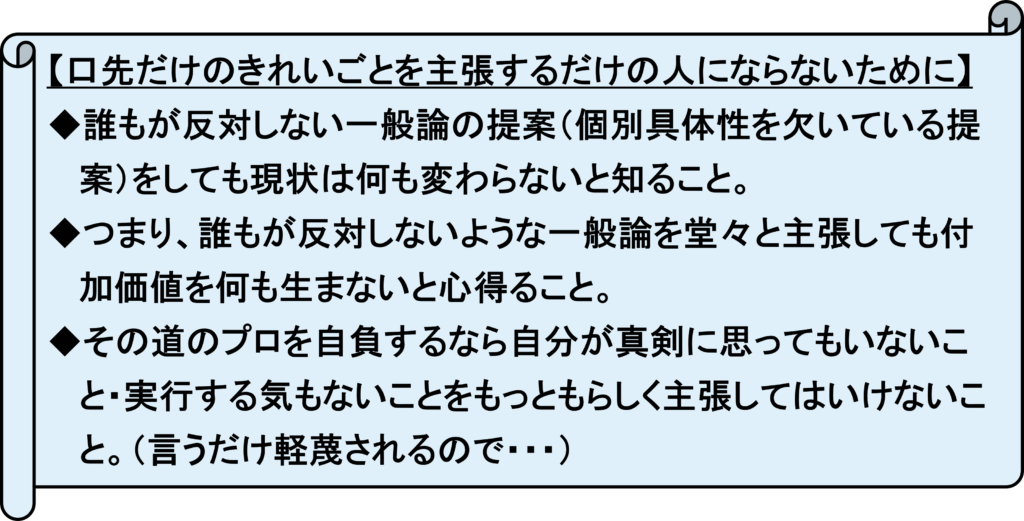
おすすめ図書
今回の記事本文で紹介した香西秀信氏の「反論の技術」という本は、第5回目の記事(議論の能力を高めるための反論の技術)のおすすめ図書としてすでにご紹介しています。同じ本を何度もおすすめ図書として挙げるのも気が引けるのですが、この本は本当に良書なのであえて今回も推薦する次第です。今回の記事本文で引用した箇所以外にも有益な指摘が満載です。機会があればぜひご一読ください。

「正論」だからといって、自分が本気で思ってもいないこと・実行する気もないこと、相手もできないだろうと自分でも薄々分かっていることを主張するのはやめましょうね。